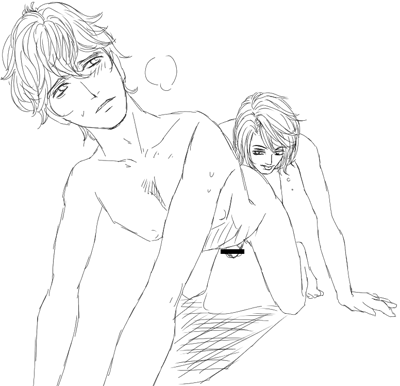
双丘をなぞる。
舌で。
「こんなおじさんにそんな事して楽しいかい?」
そう言ったのは舐められている本人、元就だ。
獣のように四つん這いになり、恥ずかしい格好をさせられているのに
随分余裕である。
だが、そんな彼に宗茂は優しく微笑んだ。
「ええ、楽しいですよ。」
これは痩せ我慢でもお世辞でも何でもなかった。
気の昂りをおしゃべりで紛らわそうとする恋人が
可愛らしくて仕方ないからだ。
まぁ、相手の事を恋人と思っているのは宗茂だけかもしれなかったが。
「僕はね、存外こういう事に慣れている方だと思う訳です。
巧者だと言ってもいい。
だけど貴方は随分余裕ですね。
僕の責めに対して。」
好きだからこそ相手の嬌声を聞きたいのに
事の最中にはおしゃべりが多過ぎる。
そろそろ明晰な思考には退場していただこう。
「さて、もう十分でしょう。
入れます。」
そう言った宗茂は即座に自身のモノを元就のそれへ
挿入した。
「くっ…!」
苦しそうに息をのんだ元就は若い雄のその質量に脚が震えた。
そして瞳にはうっすらと涙が滲んでいる。
「宗…茂。もっと浅く突いてくれないか?
僕は君みたいに若くないんだよ。
体が…、もたない。」
挿入後すぐに動かれては体がついていかないからである。
だがそんな懇願に対し、宗茂はおどけて笑ってみせる。
「言っておきますが元就公。
これはまだ貴方が思っているより入っていない。
三分の二…、程でしょうか。」
そう言って宗茂は二人の結合部が見える体位に元就を寝かせた。
確かに全て入っていなかった。
「しかし…、あぁ!」
言葉を継がせる間もなく
ひと突き、ふた突き―――。
その間隔は次第に短くなっていく。
「元就公。
精が溢れ出ていますよ。
貴方は本当に突かれるのがお好きですね。
不感症でも、僕の前戯が下手なんでもない。
こちらの口が感じすぎるんです。
成る程、元就公は
上の口も下の口もおしゃべりがお上手だ。」
それを裏付ける様に元就の押し広げられた蕾みからは
卑猥な水音がなっている。
元就の伝い落ちる精液と中で出された宗茂の精が
混ざり合って糸を引く。
「奥まで入れます?
入れたら達したままになるでしょう?
――この間もそれで大変だった。」
老いている、老いていると彼は言うが宗茂の全てを受け入れた元就は
それを全く裏切る様に精を出し続けた。
若い自分でもそんなに達する事は出来ない程に。
「俺が上手い以前の問題ですよね。」
そう言って宗茂は老体を名乗る恋人に
口づけをした――――。